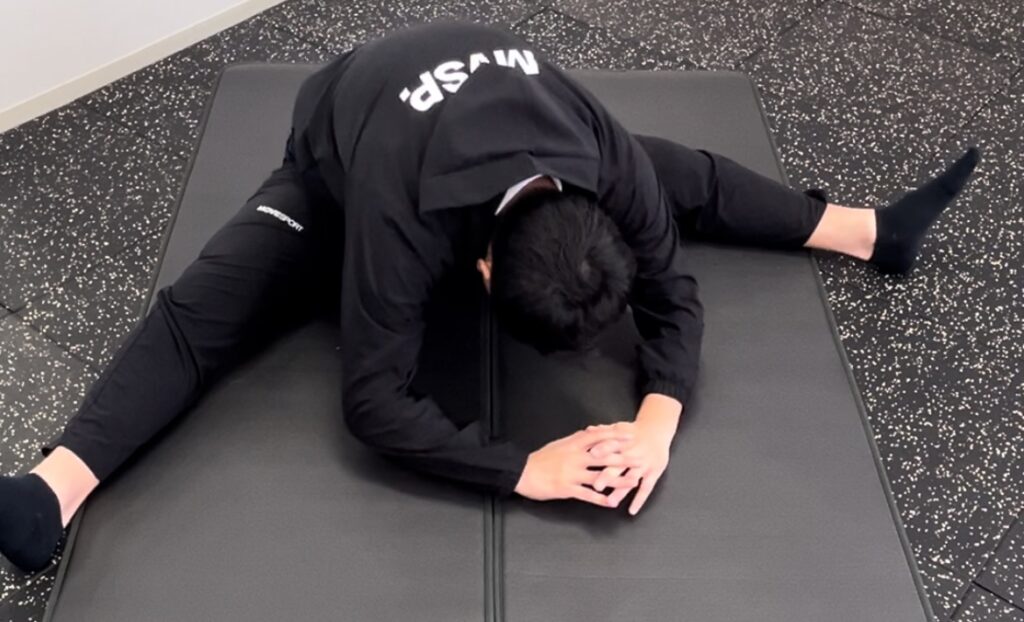セルフケアが続かない人には、いくつかの共通点があります
「セルフケアを教えてもらったけど、続かなかった」
これは決して珍しいことではありません。
むしろ、多くの方が一度は経験していることだと思います。
そして、続かなかったからといって、意志が弱いわけでも、真面目じゃないわけでもありません。
実は、セルフケアが続かない方には、いくつか共通するパターンがあります。
最初だけ、頑張りすぎてしまう
施術後や指導を受けた直後、
「よし、やるぞ」と気合が入る方はとても多いです。
中には
「50回やりました」
「100回やりました」
と、本当に一生懸命取り組んでくださる方もいます。
ただ、その結果どうなるかというと──
次の日に体がだるくなってしまい、
「今日はやめておこう」
それがきっかけで、やらなくなってしまう。
この流れ、実はとても多いです。
そして、とてももったいない。
一番よくないのは「やったり、やらなかったり」
セルフケアで一番よくないのは、
回数が少ないことではありません。
一番よくないのは、やったりやらなかったりすることです。
・今日は100回
・次の日は0回
・その次は気が向いたら少し
これでは、体は変わりにくくなってしまいます。
それだったら、
毎日30回の方が、よほど体には良い影響があります。
大切なのは、
「どれだけ頑張ったか」ではなく
「どれだけ安定して続いているか」です。
「時間があるときにやろう」は、ほぼやりません
これは、私自身の話でもあります。
「時間があるときにやろう」
そう思っていた時期もありましたが、
正直、ほとんどやりませんでした。
だから私は、
必ず毎日やっている行動の前後にくっつける
と決めました。
私の場合は「お風呂上がり」です。
お風呂上がり、水を飲む前に「30秒だけ」すると決めました。
タイミングは人それぞれでいい
お風呂上がりでなくても構いません。
・歯磨きの後
・寝る前
・夕食前
大切なのは、
「必ず毎日行う行動」とセットにすることです。
ちなみに、
「トイレに行くたびにやろう」という方もいますが、
トイレは1日に何回も行きますよね。
それだと、だんだん面倒になってしまいます(笑)
回数が多すぎるのも、続かない原因になります。
セルフケアが続かない人の3つの共通点
ここまで読んでいただくと、
セルフケアが続かない方には、次のような共通点があることが分かります。
- 最初だけ頑張りすぎてしまう
- 「時間があるときにやろう」と考えてしまう
- 回数や完璧さを求めすぎてしまう
これらは、どれも「真面目で、良くなりたい気持ちが強い」からこそ起こります。
だからこそ、やり方を少し変えるだけで、体はちゃんと変わっていきます。
セルフケアは「頑張るもの」ではありません
セルフケアは、
気合や根性でやるものではありません。
生活の中に無理なく組み込み、
淡々と続けるものです。
当院では、
あなたの生活に合った形で、
続けられるセルフケアを一緒に考えていきます。
『なぜ当院の初回は時間がかかるのか』の記事で詳しくお話ししています。
セルフケアを続けるための考え方や
短い時間でも体が変わっていく理由については、
『日々の積み重ねが体を変える』の記事で詳しくお話ししています。
「今度こそ続けたい」
そう思っている方は、ぜひ一度ご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。